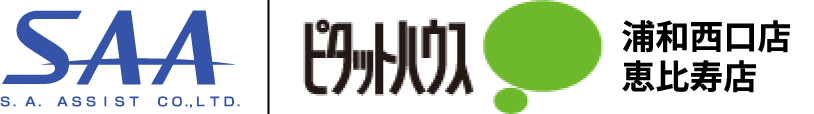相続した木造住宅は解体すべき?費用、メリット・デメリットから考える最適な選択とは

独自のノウハウにより安心・安全そしてリーズナブルに解体サービスを提供する、
ピタットハウス浦和西口店・恵比寿店を運営する株式会社エスエイアシストがお届けする解体コラム、第47回目は「相続した木造住宅の解体について」です。
ご両親やご親族から長年住み慣れた家を相続する…それは、財産を受け継ぐ喜びとともに、その後の管理や活用方法について、大きな課題を突きつけられる瞬間かもしれません。特に、相続した家屋が築年数の古い木造住宅の場合、「このままにしておくべきか、それとも解体すべきか」という選択に頭を悩ませる方は少なくないでしょう。
「この家、もう住む予定がないけどどうすればいいんだろう?」
「解体するにも、費用がどれくらいかかるか想像もつかない」
「解体した方がいいって聞くけど、本当にそうなの?」
この記事では、相続した木造家屋の解体を検討しているあなたのために、解体するメリット・デメリット、気になる費用、そして解体を決断する前に知っておくべきことについて、解体工事の専門家が分かりやすく解説します。
相続した木造家屋を解体する前に知っておきたいこと
相続した木造家屋が築年数の古い建物だった場合、さまざまなリスクを抱えている可能性があります。それらを理解することが、解体という選択肢を考える第一歩となります。
築年数による建物のリスク
木造住宅の法定耐用年数は22年とされていますが、これはあくまで税法上の目安です。しかし、築30年、40年と経つ木造家屋は、以下のような問題が生じているケースが少なくありません。
耐震性の問題
1981年以前の旧耐震基準で建てられた建物は、現在の耐震基準を満たしておらず、大地震で倒壊するリスクがあります。
建物の老朽化
屋根や外壁の劣化、雨漏り、シロアリ被害、木材の腐食などが進み、放置すると建物の安全性がさらに低下します。当然ながら風水害にも弱くなってしまっています。
空き家によるリスク
放置された空き家は、不法侵入や放火の対象になったり、景観を損ねることで近隣住民とのトラブルに発展したりする可能性があります。空き家については特別措置法も定められており、一定の条件を満たした空き家については固定資産税の住宅用地特例が受けられなくなり、持ち主の税負担が大幅に増加する可能性があります。
相続した木造家屋を解体するメリット
相続した木造家屋を解体し、更地にすることで、以下のようなメリットが生まれます。しっかりと確認して、デメリットとも比較していきましょう。
土地の売却がスムーズになる
古く老朽化した建物が建ったままだと、買い手は建物の解体費用や、建て替えにかかる手間を考慮しなければなりません。そのため、買い手が見つかりにくかったり、土地の売却価格が低くなったりする傾向があります。更地にすることで、土地としての価値が明確になり、購入希望者も増え、スムーズな売却が期待できます。
土地活用の選択肢が広がる
更地になった土地は、売却だけでなく、駐車場経営やアパート・マンションの建設、新しい住宅の建築など、さまざまな形で活用できます。相続した土地を有効活用することで、新たな収入源を生み出すことも可能です。
管理の手間と費用がなくなる
空き家を所有していると、定期的な清掃や換気、メンテナンス、固定資産税の支払いなど、多くの手間と費用がかかります。解体してしまえば、こうした管理の手間から解放されます。
特定空き家への指定を回避できる
適切に管理されていない空き家は、自治体によって「特定空き家」に指定される場合があります。特定空き家になると、前述したとおり、固定資産税の優遇措置が受けられなくなり、税金が最大6倍に跳ね上がるだけでなく、行政からの指導や命令、最悪の場合は行政代執行(強制解体)の対象となることもあるのです。
相続した木造家屋を解体するデメリット
一方で、解体にはデメリットも存在します。メリットとデメリットを比較検討することが大切です。
解体費用と手続きがかかる
木造家屋の解体には、当然ながら費用がかかります。一般的な木造住宅の解体費用の相場は、坪単価で約2万円~5万円程度です。また、解体後は法務局で滅失登記を行う必要があり、手間と費用が発生します。
固定資産税の負担が増える可能性がある
建物が建っている土地は、「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が最大で6分の1まで減額されています。しかし、家屋を解体して更地にすると、この特例が適用されなくなり、固定資産税が最大で6倍に増えてしまう可能性があります。
ただし、これはデメリットばかりではありません。更地にして土地を売却すれば、固定資産税が増える期間は短期間で済み、売却で得た収益で税金の負担を補うことができます。
相続した木造家屋の解体費用相場と注意点
木造家屋の解体費用は、以下のような要因によって変動します。
解体費用の主な内訳
本体解体工事費
建物本体の解体費用です。建物の構造や階数、面積によって決まります。
廃材処分費
解体で発生した木材や建材などの廃棄物処分費用です。廃棄物の種類や量、処分場までの距離によって変動します。
付帯工事費
内装の撤去、庭の庭石や植栽の撤去、ブロック塀や物置の解体など、本体工事以外にかかる費用です。
人件費・重機費用
作業員の日当や、解体に必要な重機のレンタル代などです。
その他諸経費
役所への届け出費用、近隣対策費用などです。
費用を抑えるためのポイント
複数の業者から相見積もりを取る
複数の解体業者から見積もりを取得することで、費用相場を把握し、適正価格で工事を依頼できます。
不用品を事前に処分しておく
解体業者に不用品の処分を依頼すると、その分費用がかさみます。事前に家具や家電などを自分で処分しておくことで、費用を抑えることができます。
補助金・助成金を活用する
自治体によっては、老朽化した空き家の解体に対して補助金や助成金を支給している場合があります。お住まいの地域の制度を調べてみましょう。
解体費用については以下のコラムも参考にしてください。
まとめ
相続した木造家屋の解体は、解体費用や手続き、税金、そして将来の土地活用など、考えるべきことがたくさんあります。特に、親から受け継いだ大切な家だからこそ、安易な判断は避けたいものです。「解体と売却、どちらが得なの?」「解体費用が想像以上にかかりそうで不安…」
そういったお悩みをお持ちの場合は、まずは解体工事の専門家に相談することをお勧めします。専門家であれば、あなたの建物の状況を正確に診断し、ご要望に合わせた最適なプランを提案してくれるでしょう!
私たちエスエイアシストでは、不動産解体業者として丁寧で綺麗、クレームのない解体・撤去工事に力を入れています。また、ピタットハウス浦和西口店・恵比寿店を運営しており、安心してご依頼いただけます。これまでも木造建築の解体や不動産の相続に関するご相談を数々と解決してきた実績がありますので、お悩みの方は、ぜひ一度エスエイアシストにご相談ください!お待ちしています。