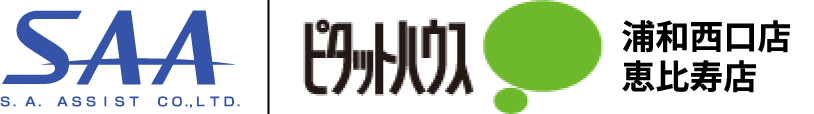再建築不可物件は更地にすべき?解体・売却・賃貸を徹底比較します!

独自のノウハウにより安心・安全そしてリーズナブルに解体サービスを提供する、
ピタットハウス浦和西口店・恵比寿店を運営する株式会社エスエイアシストがお届けする解体コラム、第49回目は「再建築不可物件について」です。
ご両親から相続した家、あるいは取得した不動産が、実は「再建築不可物件」だったと知って驚く方は少なくありません。再建築不可物件とは、その名の通り、建物を解体しても、新たに建物を建てることができない土地のことです。
「建物を解体したら、ただの空き地になってしまうのでは?」
「売るに売れないし、住む人もいない。どうすればいいんだろう…」
再建築不可物件を所有していると、こうした不安や悩みが尽きないものです。特に、老朽化が進んでいる場合には、解体するか、それともこのまま利用するかという難しい判断を迫られます。
この記事では、再建築不可物件について、その定義から、解体という選択肢のメリット・デメリット、そして売却や賃貸といった他の選択肢との比較まで、解体工事の専門家が分かりやすく解説します。
もくじ
「再建築不可物件」とは一体どんな物件なのか?
再建築不可物件とは、建築基準法上の道路に2メートル以上接していない土地に建つ建物のことです。
なぜこのようなルールがあるのでしょうか?
建築基準法では、火災や災害時に消防車や救急車などの緊急車両がスムーズに通れるよう、また日照や通風を確保するため、すべての建物が幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していることを義務付けています。これを「接道義務」と呼びます。
この条件を満たさない土地に建つ建物は、たとえ老朽化していても、一度解体してしまうと新しい建物を建てることができません。
主な要因としては、以下のケースが挙げられます。
土地が道路に全く接していない(袋地)
他の土地に完全に囲まれており、公道に出るための通路が一切ない土地です。このような土地は、緊急車両の進入はもちろん、日常生活においても不便が多いのが特徴です。
通路の幅が狭い(旗竿地)
道路に出るための通路(「旗竿地」の竿の部分)が、建築基準法で定められた2メートル未満しかない場合です。旗竿地自体は珍しくありませんが、竿の部分が2メートル以上ないと、再建築は認められません。
接している道路の幅が狭い
接している道路自体の幅が4メートル未満の場合、「セットバック」が必要です。これは、道路の中心線から2メートル後退した部分を道路と見なし、その範囲を建物や塀などから空けなければならないというルールです。このセットバックができていないと、接道義務を果たしていると認められないことがあります。
再建築不可物件を「解体」する必要はある?
「再建築不可なら、解体しても意味がないのでは?」そう考える方もいるかもしれません。しかし、老朽化した建物を放置しておくことには、非常に多くのリスクが伴います。
倒壊・火災リスク
築年数の古い建物は、地震や台風で倒壊する危険性が常にあります。また、老朽化した配線などから火災が発生するリスクも無視できません。もし倒壊や火災によって通行人や隣家に被害を与えた場合、所有者が損害賠償を請求される可能性があります。
特定空き家への指定リスク
適切な管理がなされていないと、自治体から「特定空き家」に指定される場合があります。特定空き家になると、建物を維持しているにもかかわらず固定資産税の優遇措置が受けられなくなり、税金が最大で6倍に跳ね上がります。さらに、行政からの指導や命令、最悪の場合は行政代執行による強制解体の対象となる可能性もあるのです。
管理の手間と費用
空き家を所有しているだけで、定期的な清掃や換気、メンテナンス、近隣トラブルへの対応など、多くの手間と費用がかかります。
これらのリスクを考えると、建物が老朽化している場合は、解体して更地にするという選択肢は非常に現実的な解決策と言えるでしょう。
再建築不可物件を解体するメリット・デメリット
再建築不可物件の建物は、解体することで多くのメリットが生まれる一方で、デメリットも存在します。
解体するメリット
リスクの回避
老朽化による倒壊や火災、特定空き家への指定といったリスクから完全に解放されます。建物がなくなれば、これらの物理的・法的なリスクはゼロになります。
土地の管理が容易になる
建物がなくなれば、定期的な清掃やメンテナンス、修繕の手間が一切不要になります。土地の雑草を刈る程度の簡単な管理で済むため、所有者にとっての精神的・経済的な負担が大幅に軽減されます。
売却・活用の可能性が広がる
再建築不可物件は、建物を解体することで売却しやすくなる場合があります。建物が建ったままだと、買い手は建物の状態や解体費用を考慮しなければならず、購入のハードルが非常に高くなります。更地にすることで、土地としての価値が明確になり、購入希望者が増え、スムーズな売却が期待できます。
解体するデメリット
解体費用がかかる
当然ですが、建物を解体するには費用が発生します。木造家屋であれば坪単価で2万円~5万円程度が相場ですが、建物の大きさや状態、立地によってはさらに費用がかかることもあります。
固定資産税が上がる
建物が建っている土地は「住宅用地の特例」により、固定資産税が最大で6分の1に減額されています。しかし、解体して更地にすると、この特例が適用されなくなり、固定資産税が最大で6倍に跳ね上がる可能性があります。ただし、売却を前提としていれば、この負担は一時的なものとなります。
再建築不可物件の活用方法:売却と賃貸の比較
再建築不可物件は、解体して更地にする以外にも、売却や賃貸といった活用方法も考えられます。
再建築不可物件を売却する
再建築不可物件は、一般の不動産市場では需要が低く、買い手が見つかりにくいのが現状です。しかし、特定の需要を持つ買い手には、更地にしたほうが売却しやすくなります。
隣地の所有者
隣地の所有者にとっては、自分の土地と合わせて再建築可能な土地にできる可能性があるため、高値で買い取ってもらえるケースがあります。この場合、解体費用を上回るメリットが得られることも少なくありません。
建て替えを必要としない事業者
駐車場経営、資材置き場、家庭菜園など、建物を必要としない事業を検討している事業者であれば、更地の状態で取得するメリットがあります。
リフォーム目的の投資家
建物がまだ利用可能な状態であれば、大掛かりなリフォームを施して再販したり、賃貸に出したりする目的で購入する投資家もいます。
再建築不可物件を賃貸に出す
建物がまだ利用可能な状態であれば、賃貸に出して家賃収入を得るという選択肢もあります。
売却や賃貸にするメリット
解体費用をかけずに収入を得られる点が最大のメリットです。また、建物が建っているため固定資産税の優遇措置を維持できます。
売却や賃貸にするデメリット
しかし、再建築不可物件は借り手が見つかりにくく、家賃相場も低くなる傾向にあります。さらに、賃貸として貸し出すには、建物の修繕や管理、契約トラブルへの対応など、多くの手間とリスクが伴います。
まとめ
再建築不可物件の解体は、通常の解体工事とは異なり、その後の土地活用や法的な問題が複雑に絡み合います。安易な判断は、将来的な大きな損失につながりかねません。
「再建築不可物件って本当に売れるの?」
「この建物を解体して更地にすべきか、どう判断すればいいの?」
「誰に相談すればいいのか分からない…」
そうしたお悩みをお持ちの場合は、まずは解体工事の専門家や、不動産売買に強い専門家に相談することをお勧めします。専門家であれば、あなたの建物の状況や土地の価値を正確に評価し、最適な解決策を提案してくれます。
もし、どこから手をつければ良いか分からなかったり、一人で片づけを進めるのが不安に感じたりした場合は、無理をせず、専門家である解体業者に相談してみましょう。
私たちエスエイアシストでは、不動産解体業者として丁寧で綺麗、クレームのない解体・撤去工事に力を入れています。また、ピタットハウス浦和西口店・恵比寿店を運営しており、安心してご依頼いただけます。これまでも様々な再建築不可物件の解体や土地の売却に関するご相談を数々と解決してきた実績がありますので、お悩みの方は、ぜひ一度エスエイアシストにご相談ください!お待ちしています。