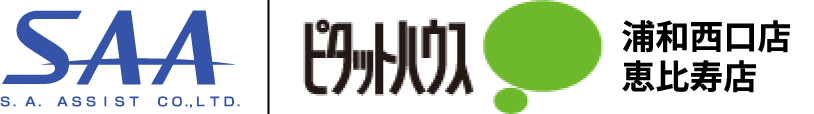専門家が解説!連棟式建物の解体で失敗しないために知っておくべきこと

独自のノウハウにより安心・安全そしてリーズナブルに解体サービスを提供する、
ピタットハウス浦和西口店・恵比寿店を運営する株式会社エスエイアシストがお届けする解体コラム、第45回目は「連棟式建物の解体について」です。
「建物を解体したい」そう考えたとき、多くの方はまず「どの業者に頼もうか?」や「費用はいくらだろう?」といった点を思い浮かべるかもしれません。しかし、もしあなたの建物が連棟式建物だった場合、通常の戸建て住宅の解体とは異なる、特別な知識と注意が必要になります。
連棟式建物とは、壁を共有して複数の住戸が連なっている住宅のことで、特に古い住宅に多く見られます。解体や建て替えを考えたとき、この連棟式建物ならではの複雑なルールや手続きを知らずに進めてしまうと、思わぬトラブルや大きな費用負担に繋がる可能性も…!
この記事では、連棟式建物の解体を検討している方のために、どのような物件が連棟式建物に該当するのか、そして、解体時に特に注意すべきポイントやトラブルを避けるための方法について、解体工事の専門家が分かりやすく解説します。
もくじ
どのような建物が「連棟式建物」と呼ばれるのか
連棟式建物とは、壁や屋根を共有して複数の住戸が一体となっている建物のことです。外見は複数の戸建てが並んでいるように見えますが、構造上は1つの建物として建てられています。代表的なものとして「テラスハウス」や「タウンハウス」といった住宅が挙げられます。
ご自身の建物が連棟式建物かどうかを判断するには、法務局で取得できる「建物謄本(登記簿謄本)」で確認するのが最も確実な方法です。
建物謄本が「1棟の建物」として登記されている場合、それは連棟式建物、特に後述するタウンハウスの可能性が高いと言えるでしょう。一方、外見が連棟式に見えても、建物謄本が各住戸ごとに独立して登記されている場合は、隣家と壁を共有していても法的には独立した戸建て住宅と見なされます。
連棟式建物は「テラスハウス」と「タウンハウス」に分かれる
連棟式建物は、その土地(敷地)の所有形態によって、大きく2つのタイプに分けられます。それぞれの違いを理解することが、解体時の難易度や手続きを把握する上で非常に重要です。
敷地が各住戸で分かれている「テラスハウス」
テラスハウスは、外見は壁を共有して連なっていますが、敷地が各住戸ごとに分筆(分割)され、それぞれが独立した所有権を持っているタイプです。
法的には、各住戸が敷地と建物の両方で独立しているため、所有者の意向で自由に売買や解体を行えます。ただし、隣家と共有している壁を解体・撤去する際には、隣家の外壁を新たに設ける必要があるため、そのための費用や工法について事前に隣家と協議し、承諾を得る必要があります。
敷地を共有している「タウンハウス」
一方、タウンハウスは、複数の住戸が連なっており、敷地全体を住人全員で共有しているタイプです。敷地が分筆されておらず、住人全員が敷地全体の所有権を「共有」している点がテラスハウスとの大きな違いです。
このタイプの建物は、解体や建て替えを行う際の難易度が非常に高くなります。その理由は、建物全体が1つの登記簿で「1棟の建物」として登記されている場合が多く、1人の所有者が勝手に建物を解体することはできないためです。解体には、原則として共有者の最低4/5以上、可能であれば全員の同意が必要とされています。
解体・切り離しは非常に難しい!タウンハウスに潜むリスク
タウンハウスは、その構造と登記の特性上、解体や切り離しが非常に困難で、様々なリスクを伴います。
解体には全所有者の同意が原則必要
先述のとおり、タウンハウスの解体は、原則として、最低でも所有者最低4/5以上、可能であれば全員の同意が必要です。1人でも反対する所有者がいれば、解体を進めることは難しいでしょう。これは、共有している建物全体に影響を与える行為だからです。
所有者同士の意見がまとまらず、解体を断念せざるを得ないケースは少なくありません。
連棟式建物の切り離しが抱える課題
仮に隣の住戸と切り離して自分の住戸だけを解体する場合でも、大きな問題が発生します。建物は一体構造のため、切り離し工事は建物の構造的なバランスを崩し、隣の住戸に影響を及ぼす可能性があるのです。
具体的には、解体した部分の壁がなくなることで、隣家の外壁がむき出しになり、雨漏りや耐震性の低下を招く恐れがあります。そのため、切り離した部分に新たな外壁を設置する工事が必要になりますが、これも次項の建築基準法上の「耐火構造」や「防火区画」のルールに抵触しないよう、厳密な設計と施工が求められるでしょう。
建築基準法に抵触するリスク
連棟式建物の切り離しには、建築基準法上の厳しいルールが存在します。例えば、建物と建物の間には通常、延焼を防ぐための「防火壁」や、建物が倒壊した際に隣の建物に影響を与えないための「構造的な分離」が求められるのです。また、「接道義務」や「斜線制限」、「建蔽率」や「容積率」など様々な決まりがあります。
一体構造の連棟式建物を切り離すと、この基準を満たさない状態になり、違法建築物と見なされるリスクがあるでしょう。ルールを守らずに工事を進めてしまうと、是正勧告を受けたり、最悪の場合、行政指導の対象になったりすることもあります。
他の所有者とのトラブルや裁判沙汰に発展する可能性も
最も大きなリスクは、隣家や他の所有者とのトラブルです。同意なしに解体を進めたり、工事によって隣家に損害を与えたりした場合、損害賠償を請求される可能性があります。
共有部分の解体・切り離しは、単に工事の問題に留まらず、所有者間の「所有権」や「合意」といった複雑な法的な問題が絡み合うためです。そのため、一度トラブルが発生すると、解決までに時間と労力がかかり、裁判沙汰に発展するケースも珍しくありません。
連棟式建物の解体で失敗しないために、まずは専門家にご相談を
連棟式建物の解体は、通常の戸建て住宅の解体とは一線を画す、非常に専門的な知識と経験が求められる工事です。特に、建物謄本が一体で登記されているタウンハウスの場合、その難易度は格段に上がります。
もし、あなたが所有する連棟式建物の解体で不安を感じているなら、最初に専門的な知識と豊富な実績を持つ解体業者に相談することをお勧めします。専門家であれば、あなたの建物の状況を正確に把握し、法的なリスクや隣家とのトラブルを回避するための最適な方法を提案してくれるはずです。
まとめ
前述のとおり、連棟式建物、とくにタウンハウスの場合は、切り離しや解体する際に様々な課題や注意点があります。「どうやって隣家と話を進めたら良いのか」「解体は可能なのか」「いくら費用がかかるのか」といった疑問や不安をお持ちの際は、連棟式建物の解体や切り離し実績のある業者に相談、見積もりを依頼しましょう。
私たちエスエイアシストでは、不動産解体業者として丁寧で綺麗、クレームのない解体・撤去工事に力を入れています。また、ピタットハウス浦和西口店・恵比寿店を運営しており、安心してご依頼いただけます。これまでも連棟式建物の解体に関するご相談を数々と解決してきた実績がありますので、お悩みの方は、ぜひ一度エスエイアシストにご相談ください!お待ちしています。
こちらの記事もどうぞ
CONTACT US
住宅や建物の解体なら
エイスエイアシストにお任せ!
ご相談・お見積りは無料です。まずはお気軽にご相談ください